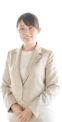顧客概要
K様(80代・男性)と妻のB様(70代)は東京都台東区にお住まいのご夫婦で子供はおらず、ご両親はすでに他界、お二人とも早くにご兄弟姉妹を亡くし、甥姪もいらっしゃいません。親族には従兄弟姉妹が複数名いますが、密接な関係の方は限られているとのことでした。
B様は収益アパートを所有し、K様は自宅と金融資産を保有。それぞれに不動産と預金等の財産を持つものの、信頼できる相続人や管理者が身近にいないことに不安を感じられていました。
ご相談内容
B様は病気療養中で介護施設に入所中。日常的な財産管理やアパートの維持管理などは、実質的にK様が代行していましたが、名義上の制約があり、スムーズな対応が困難になっていました。
またK様自身も高齢で持病があることから、今後の管理体制の継続性、死後の手続き、財産の行方について深刻な懸念を抱えておられました。特に、どちらか一方が先に亡くなった場合の相続処理や、相続人不在時の国庫帰属リスクがありました。
解決策1:商事信託の導入と信託会社による一元管理
これらの問題を整理した結果、K様・B様双方にとって最も確実な手段として、信託会社を受託者とする商事信託スキームを導入することにしました。
【商事信託スキームの内容】
- 委託者兼受益者:B様
- 受託者:信託会社
- 信託財産:収益アパート、金融資産の一部
- 信託の目的:B様の生活費支出とアパート管理の継続
- 信託終了時の帰属先:K様 → 従姉妹 → 従姉妹の子
このように、信託会社が受託者としてアパートと財産を管理する体制を整えることで、K様が体調を崩した場合や先に亡くなった場合でも、B様の生活に支障が出ないよう配慮しました。
解決策2:遺言書の作成
すべての財産を信託してしまうと、信託後の委託者の生活費等の捻出が難しくなってしまうため、預貯金の一部は信託せずに遺言を作成しました。
遺言の内容は次の通りです。
・信託していない預貯金などのすべての財産→K様へ相続→K様が亡くなっていた場合は従姉妹
また、K様も一緒に遺言書を作成し、すべての財産をB様へ相続→B様が亡くなっていた場合は従姉妹に承継させることができるようにしました。
商事信託を採用したメリット
- 受託者の安定性と専門性
信託会社は法人であるため、個人と違って死亡や認知症による信託終了のリスクがありません。長期的かつ安定的に管理が継続できます。 - 煩雑な不動産管理の一元化
信託会社が受託者として直接管理するため、アパートの空室対応や修繕、家賃管理、税務対応も一括して任せられます。 - スムーズな財産承継設計
あらかじめ定めた帰属権利者へ信託財産が確実に引き継がれる設計となっており、国庫帰属を避けることが可能です。 - 信頼性と第三者性の確保
家族や親族間の利害関係から距離を置き、中立的立場で管理されるため、トラブルの予防にもなります。
お客様からのメッセージ
「私たち夫婦のように、支える身内が少ない者にとっては、信託会社という第三者のプロに任せることがどれほど安心につながるかを実感しました。最初は信託会社ってなんだろう、家族のことなのになんて大げさだと思っていましたが、今はその判断がベストだったと確信しています。また、遺言書も作っておくことで、私たちの財産全ての承継先を決めておくことができました。私たちの財産はどうなってしまうんだろう、と不安だったので安心しました。」