
廣木 涼
[相続終活のリアル]
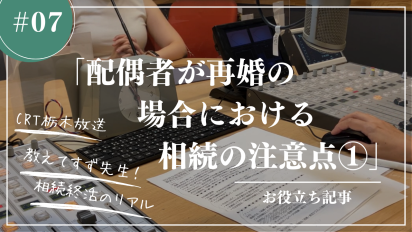
相続専門の司法書士廣木涼です。
配偶者が再婚の場合に特有の相続リスクと対策について、ご紹介します。
家族関係は、夫と妻、夫が再婚で前妻との間に子どもがいるというケースで考えてみましょう。
妻に相続が発生した場合、相続人は夫と妻の兄弟姉妹です。法定相続分は夫が4分の3、兄弟姉妹が全員で4分の1です。夫は妻の兄弟姉妹と妻の遺した財産についてどう分けるかの話し合いをする必要があります。
そして、夫が亡くなった後は、夫が妻から相続した財産は夫の財産として夫の子どもに相続されることとなります。妻としてはいくら夫の子どもであっても実際には会ったこともない、というケースも多いのではないでしょうか。夫の子どもに対する気持ちと妻の夫の子どもに対する気持ちに乖離が生じることも多いことも十分考えられます。せめて自分が働いて稼いだ分は、夫の子供よりも自分の甥姪に財産を遺したい、と考える方もいらっしゃるでしょう。妻としては、将来的には夫が相続した財産が夫の子どもに渡ることも念頭に置いて、自宅や金融資産など、夫に渡すものをどうするか決めておく必要があります。
夫に相続が発生した場合、相続人は妻と夫の子どもです。法定相続分は妻2分の1、子ども2分の1です。
たとえば自宅の名義が夫で夫の主な財産が自宅のみ、預金がほとんどないような場合、妻がもし「自宅に住んでいるから自宅は自分の名義にして欲しい」と言っても、自宅不動産の価値が3000万円で預金が100万だった場合、法定相続分だと妻と子どもが2分の1ずつになり、子どもとしては約1500万円を自分の権利として主張ができます。子どもから法定相続分1/2の約1500万を請求されてしまうと、なかなかぽんっと支払える金額ではないですよね。そうすると自宅不動産を売らざるを得なくなってしまう可能性もでてきます。
保険は、受取人固有の財産と言って、相続財産とは別扱いで受取人を指定することが可能です。
保険を活用することで相続のトラブルを防止する対策も考えられます。
再婚の場合は、相続が発生する前に対策をしておくことが大切です。例えば、夫が病気になってから遺言を書いてもらいたいと思っても、死が目の前に迫っているような状態の夫に遺言の話しをするのはなかなか難しいものがあります。相続に何かしら不安がある方はいち早く専門家に相談したり、元気なうちに家族で話し合いを持ったりすることが大切です。そうすることで後々のトラブルを回避できる可能性が高まります。
重要なのは、相続が起きた時の財産の行先を知ること、家族間で事前に十分な話し合いを行い、互いの意向を理解しておくこと、そして遺言書など法的に明確な形で財産の行先を決めておくことです。
相続、終活に関する情報発信を通して、トラブルになる前に気を付けた方がいいことを皆さまに知ってもらい、ご自身やご家族が困らないような対策をするきっかけになってもらえればと思っています。

廣木
ご質問やご相談がございましたら、お気軽にお問合せください。
専門スタッフが丁寧に対応いたします。
対応地域
日本全国