
廣木 涼
[相続終活のリアル]
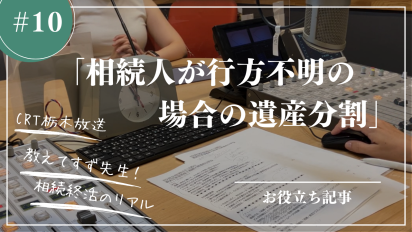
相続専門の司法書士廣木涼です。
遺産分割のトラブル事例として、意外と多いケースが「行方不明の相続人がいるケース」です。今回は、「行方不明の相続人がいるケース」での対処方法についてご紹介していきます。
一つの事例として、昔に親子喧嘩をして、息子さんが家を飛び出して以来、会ってもいないし連絡も取っていない、というケースが挙げられます。
いざ相続が発生して、連絡を取ってみようとしても取れず、手紙を出してみても届かない、なんてこともあります。「連絡が取れないならしょうがない、私たちだけで話し合っちゃえばいいんじゃないの?」と思うかもしれません。ですが、そういうわけにはいきません。遺産分割協議は、相続人全員で行うことが要件です。行方不明者がいる場合、その要件を満たさないので、遺産分割協議を行うことができないのです。
では、どのようにすればいいのでしょうか?対応方法として、次の2つの方法があります。
①失踪宣告
生死不明の状態が7年続いた場合に、「死亡したものとみなす」制度です。
ただし、「生死不明の状態」とは単なる連絡不通だけでは認められません。
そのため、実務では比較的使用頻度が低い手続きです
②不在者財産管理人の選任
失踪宣告より一般的な解決方法です。裁判所に申立てを行い、行方不明者の代理人を選任します。
実務では、こちらの方法を採用することが多いです。
まずは、行方不明者の住所地の調査をします。住所地は役所で取得できる住民票や戸籍の附票を確認します。住民票や戸籍の附票に記載された住所に住んでいる可能性が高いので、お手紙を出したり、実際に住所地に行ってみて住んでいるかどうか確認します。そこで実際に住んでいることが分かれば、不在者財産管理人は選任せず、遺産分割協議への協力をお願いし、手続きを進めることができます。
ですが、住民票を異動させていないと、住所地に行っても住んでいる形跡がなかったり、別の人が住んでいる場合もあります。そうなるとこれ以上行方を調べることができませんので、裁判所に申立て、不在者財産管理人を選任してもらうことになります。
裁判所での選任手続きは、申立てをしてすぐに管理人が決まるわけではありません。裁判所側も不在者を探します。裁判所から、年金事務所などの関係各所に照会をかけ、履歴を調べ、就労している形跡がある、ということで不在者が見つかり、解決につながることもあります。
不在者財産管理人にはどんな人がなるのでしょうか。裁判所が不在者財産管理人を選ぶと、弁護士や司法書士が選ばれることになり、費用がかかってしまいます。そのため、申立ての際、任意の候補者を立てることができます。ですが、不在者の財産をしっかり管理してもらうために、遺産分割に関係ない人でないといけません。
また、不在者財産管理人の選任には時間がかかります。預金仮払の制度はありますが、原則として遺産分割協議ができるまでの間、相続財産は凍結されたままです。不在者財産管理人が選任されるまで遺産分割ができず、親の口座から葬儀費用など支払いたいのに、お金を下ろせず、困ってしまうこともあります。
行方不明の相続人がいると、予期せぬ形で相続手続きが複雑になってしまう可能性があります。家族に連絡が取れない人がいるとどうなるかを知ったうえで、相続が起きる前に、早めの対策が重要です。
相続、終活に関する情報発信を通して、トラブルになる前に気を付けた方がいいことを皆さまに知ってもらい、ご自身やご家族が困らないような対策をするきっかけになってもらえればと思っています。

廣木
ご質問やご相談がございましたら、お気軽にお問合せください。
専門スタッフが丁寧に対応いたします。
対応地域
日本全国